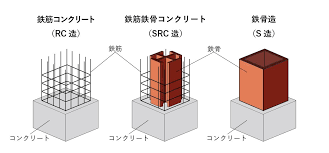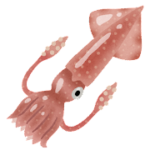ページコンテンツ
イントロダクション
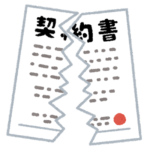
ある男が宝くじに当たり3億円手に入れた、日本の銀行では不安と考え、スイス銀行まで飛行機に乗って預金に行った。
銀行で3億円入ったバッグを手にして行員にヒソヒソ声で「預金したい」と伝えた。
するとスイス人の行員は3億円分の米ドル札を見てニッコリ。
「心配いりませんよ。スイスでは貧乏は恥ではありませんよ。少額でも恥じることはありません」
と慰めた。スイス銀行では3億円程度は大金ではないらしい。
預金を断られなかっただけ良かったのかも。預金も一つの契約です。
令和 2年度 第 12問
〔問 12〕
Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの実印を押捺なつした委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが作成したAの委任状を真正なものとCが信じ、かつ信じたことに過失がないときには、当該売買契約は有効である。
2 当該売買契約締結後に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。
3 Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないときは、AはDに自らの権利を主張できない。
4 売買契約後にBに代理権がなかったことを知ったCが、Aに対し「7日以内に追認するかどうかを確答して欲しい」旨の催告をしたが、Aがその契約の内容を判断する能力があるにもかかわらず、その期間内に確答しなかったときは、その契約を追認したものとみなされる。
解答と解説
すべて、正しく見えてしまう。
1、Cは過失なく信じた。よって有効。
2、契約後に正式に相続したBとCの契約は有効。

3、Cはもちろん無過失。Dも無過失。売買は有効。
4、追認要求を受けたAが無視。この場合追認したものとして契約は有効。
無過失に信じた契約は有効なのか?
では、契約に関する民法を見てゆきましょう。
A=マンション所有者
B=Aの子供で同居人。委任状をAの承諾なしに実印を押して作成。無権代理。
C=第三者のマンション購入者。善意・無過失。
D=転購入者C~D善意・無過失。
1 Bが作成したAの委任状を真正なものとCが信じ、かつ信じたことに過失がないときには、当該売買契約は有効である。
A(所有者)はこの場合全くこの売買に関与していない。A所有のマンションの一室であるからAの意志は必要。
・Bを代理とするという証明や事実。
・過去に代理にした事がある。
こういった事が全く無い場合(今回の事例)
表見代理(Aに帰属する責任が何らかの形である場合)が認められないので、有効ではない!
第113条【
よって ❌。
2 当該売買契約締結後に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。
B(無権代理)とC(善意・無過失)間で売買契約締結後にA(所有者)が死亡し、Bが単独相続した場合契約は当然有効である。?
民法第113条に本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。とあり、本人が追認すれば有効になる。本人(A)の権限がBに移行したのだから、これはOK.
よって、 ◯ 。
3 Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないときは、AはDに自らの権利を主張できない。
- 第113条1、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2,追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
C(善意・無過失)がD(善意・無過失)にマンションを転売した。
この場合、B(無権代理)C(善意・無過失)間の契約は無効であるから、C,D間の契約は無効。よって、A(所有者)はD(善意・無過失)に対して、権利を主張できる。
よってこの選択肢は間違い。 ❌ です。
4 売買契約後にBに代理権がなかったことを知ったCが、Aに対し「7日以内に追認するかどうかを確答して欲しい」旨の催告をしたが、Aがその契約の内容を判断する能力があるにもかかわらず、その期間内に確答しなかったときは、その契約を追認したものとみなされる。
第114条【
この条文から追認したものとみなす。ではなく 追認を拒絶したものとみなす。
です。 ❌
この問題の答えは 2 です。